環境建築デザイン学科

強い意志と高い倫理感で社会と対峙し、地域環境と調和した生活空間を構築する能力を養うため、その理論と技術を学びます。「環境学」という視座から、新しい時代の建築・ランドスケープ・都市の創造に挑戦する、すぐれた建築家およびプロフェッショナルを育てます。実際の建築や都市計画・まちづくりの実践など、現場で身体を動かして、体験をもとにイメージや空間を創り出す能力を養います。
学びのポイント
旺盛な行動力をたずさえた本学科の学生は、琵琶湖という恵まれた環境を余すことなく勉学の糧としています。フィールドワークを重ね、建築・ランドスケープ作品を建造し、周辺地域のまちづくりに積極的に取り組んでいます。世界の建築・都市デザインの動向にも敏感で、アジアの都市や地域環境の創造につながる調査を手がけるなど、活躍の場は大きく広がっています。また、講演会の開催など、学生の活発な自主活動も特徴です。世界的に活躍する学科教員は、学生のセンスに磨きをかけることを指針に教育・研究を実践しています。
-
ポイント1
-
幅広い「環境建築デザイン」から見つける得意分野
建築計画・設計、造園・ランドスケープ、都市・地域計画、建築史・空間論、環境工学、建築構造・安全防災など、広範な分野を学べます。
-
ポイント2
-
実践形式で高める、イメージを形にする力
実際の現場を想定した実習では、複雑な条件や要求をひとつの空間・イメージにまとめる訓練を行います。
-
ポイント3
-
「環境学」という視座から創造する建築・都市の未来
環境生態学、環境政策・計画学、生物資源管理学と共生した学びから、これからの生活空間・地域環境を追求します。
学びのステップ
計画
| 専門科目の例 | 1年次:地域環境計画 2年次:景観計画 3年次:都市・地域計画、建築生産施、 建築法規 4年次:環境行動論 |
|---|
デザイン
| 専門科目の例 | 1年次:建築一般構造 2年次:環境設計I、ランドスケープデザイン、環境共生デザイン 3年次:環境設計II、サスティナブルデザイン論、環境職能論 |
|---|
演習
| 専門科目の例 | 1年次:イメージ表現法、環境フィールドワークI、設計基礎演習 2年次:設計演習I、環境フィールドワークII、設計演習II、 地域産学連携実習、CAD演習I 3年次:設計演習III、環境フィールドワークIII、CAD演習II、 環境・建築デザイン演習、設計演習IV 4年次:卒業研究・卒業制作I、卒業研究・卒業制作II |
|---|
歴史・理論
| 専門科目の例 | 2年次:西洋建築・思潮史、比較都市論、環境造形論、内部空間論 3年次:環境行動論、アジア建築史、環境技術史、日本建築史 4年次:文化財・保存修景論A |
|---|
技術
| 専門科目の例 | 1年次:構造計画、建築数学・物理 2年次:構造力学I 3年次:構造力学II、建築環境工学演習、アジア建築史、環境技術史、環境設備 |
|---|
専門科目の例
合同講評会

設計演習ⅠからIVで建築造形の基本、実践的な設計につなげる設計過程、そしてより⾼度な計画・デザイン⼿法を⾝につけ、総合的な提案⼒を学び、合同講評会にて発表を⾏います。
木匠塾

「木匠塾」は、地域の課題を、木によるものづくりで解決することを目指した科目です。地域との関わりを重視し、設計から制作までを学生自身が主体的に行う、本学科の特徴的な科目の1つです。
研究室紹介
- 建築デザイン 芦澤 竜一 研究室
-
芦澤 竜一 教授

研究室について
建築は、地球上に計画される人間のための環境を形成する人工物です。循環する地球の運動をよく理解し、自然環境と呼応する建築のデザイン手法を研究しています。時代は常に変わっていきますが、人間が求める根源的な喜びは決して自立したものではなく、自然現象を感じたり、人と人との出会いなど自分以外の存在とのつながりだと考えています。建築によって、感性と知性を伴った自然と人々との豊かな関係性をいかに築けるか日々思考しています。メッセージ
現代社会において我々を取り巻く複雑な状況を分析しながら、建築が持つ可能性を探っていきましょう。
- ランドスケープデザイン 村上 修一 研究室
-
村上 修一 教授

- 環境建築デザイン 西澤 俊理 研究室
-
西澤 俊理 准教授
準備中
- 建築史・意匠 玉田 浩之 研究室
-
玉田 浩之 准教授
準備中
- 日本建築史 髙屋 麻里子 研究室
-
髙屋 麻里子 講師

研究室について
日本の建築の歴史のなかでも中世からの土蔵が専門です。中世の土蔵は現存が知られていませんから、様々な史料から読み解いてゆきます。これまでに絵画史料を対象としてきたこともあり、漫画やゲームの建築表現にも注目しています。中世といえば戦国期ですが、もちろん土蔵と城郭は大いに関係があります。近世以降の武家住宅やGISを用いた絵図の研究なども、こつこと調べる楽しみがあります。とはいえ、とても地味な分野です。メッセージ
日本の建築は日本の文化に基づいています。最もわかりやすい例は、ガンダムです。
- 建築空間・意匠論 大室 祐介 研究室
-
大室 祐介 講師
準備中
- 都市空間デザイン・都市建築史 ホアン研究室
-
ヒメネス ベルデホ ホアン ラモン 准教授

研究室について
都市のデザインと未来を考えるためには、現在の都市を考察する必要があります。そのためには過去から現在までの都市の変容を考察する必要があります。その形成、環境との関係、伝統的な建築と現代建築、テーマは大変広範囲に及びます。世界のすべての都市には歴史があります。したがって、私たちはすべての都市から学ぶことができます。異なる文化や異なる時代に応じた都市と建築の多様性について、私たちはどのように研究を進めるべきでしょうか? 一緒に考えましょう。メッセージ
日本だけでなく、世界に目を向けていろいろなことを学んでいきましょう!
- 都市計画史・建築計画 川井 操 研究室
-
川井 操 准教授

研究室について
まちにある文化や土地の記憶、人々の生活をよく観察することをモットーにしています。特にアジアのまちや建築には、そのルーツに必ず、政治、宗教、文化、地理環境の要素が数多く含まれています。以上をフィールドワークを基にして解明し、国際ワークショップや研究、設計を通じて、国際的に活躍できる人材を育成します。メッセージ
まちや土地の持っているポテンシャルをよく考えて、その特性を最大限に生かした設計を心がけましょう。
- 都市計画 轟 慎一 研究室
-
轟 慎一 准教授

研究室について
都市・集落の空間・コミュニティ・環境の構造とその計画論・まちづくり、特に、生活と空間の関係性に着目した計画論的研究を行なっています。「生活史・生業史と空間構造」「地域環境と生活景」「都市計画システムと事業展開」「景観の保全・活用」「人口減少時代の都市・地方と少子高齢社会」「定住環境としての中心市街地・歴史的街区・集合住宅・郊外住宅地・農山漁村」「地域居住と持続・再生」等をテーマとしています。メッセージ
建築学生が現場から得るものは、 結果だけではありません。 あなたが自身と向き合うかけがえのない時間です。
- 建築構造デザイン 陶器 浩一 研究室
-
陶器 浩一 教授

研究室について
建築空間をかたちづくる素材にはいろいろなものがあります。素材と技術、時代のニーズが関連し合って建築空間は発達して来ました。今、技術の進歩は目覚しく、建築空間の可能性は大きく拡がっています。一方で、コンピュータテクノロジーの進化は人間の創造力を退化させている面もあります。ものづくりの原点に立ち戻り、従来見出されていなかった素材の特性を引き出して、新たな空間の可能性を追求するのがこの研究室のテーマです。出来る限り実際のプロジェクトと関連させてゆくつもりです。メッセージ
頭と身体を動かそう!
- 構造工学 高田 豊文 研究室
-
高田 豊文 教授

研究室について
私が専門とする「建築構造学」は、物理学や数学などを駆使して、建物や人々の安全・安心に貢献しようとする学問です。
コンピュータを用いた建物の構造解析の研究や、木構造に関する解析・実験の研究に取り組んでいます。特に、木構造の研究は、木に関わる地域の産業だけでなく、琵琶湖を取り巻く森林の管理と整備にも密接に関わっています。建築構造学の知識が、環境保全や地域の活性化にも役立ちます。メッセージ
興味と疑問を持って建物を見ると、設計した人たち・建てた人たちの考え方や工夫に気がつくでしょう。
- 構造システム 永井 拓生 研究室
-
永井 拓生 講師

研究室について
人の願い、想いを素材に託すこと、それがものづくりの原点です。建築を作るには、重力にあらがい、地震・台風・大雪など様々な外力に抵抗する強固でしなやかな構造が必要です。しかしその方法は、現代の一般的な方法に限る必要は、決してありません。私達は、鉄筋コンクリート・鉄骨・木造といった現代的技術だけでなく、土・石・竹といった、地球上のどこにでもある身近で素朴な材料でも、建築の素材として使う事ができないか、研究や工法の開発を行っています。メッセージ
ものづくりとは「素材に思いを託す」ことです。身近にある素材や技術を建築に活かせないか、考えてみましょう。
- 建築環境デザイン・建築再生 大井 鉄也 研究室
-
大井 鉄也 教授
準備中
- 居住環境工学 鄭 新源 研究室
-
鄭 新源 講師
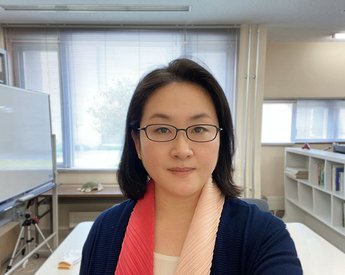
研究室について
建築は、社会が求める様々な価値の中で総合的に評価されるものですが、その中でも人間が生活する環境として快適な空間づくりを目標に、光・音・熱・空気など建築の物理要素と人間との関係を明らかにする研究を行っています。実験等による心理評価・行動と環境刺激・居住環境情報との関係を構造化する基礎的な内容から、住宅の温熱快適性、オフィスの知的生産性、学校教室の学習効率等、実使用空間に対する調査・評価を行い、快適な建築空間の作り方と使い方を提案します。メッセージ
建築要素と人間の感覚が相互的にどのような関わっているかを探り、より暮らしやすい空間を作っていきましょう。
TEACHER'S VOICE

本学の環境建築デザイン学科は、工学部ではなく、環境科学部にあります。これは、これまでの工学的建築の枠組みや専門性を越えて、自然と人間・社会との関係や地域に根ざした視点を重視するという理由からです。
本学科では、木・竹・葦などの自然素材によるものづくりや国際建築ワークショップなど、学外実習・課外活動が充実しています。
環境科学部 環境建築デザイン学科長
村上 修一 教授
CAMPUS LIFE
STUDENT'S VOICE
環境科学部 環境建築デザイン学科
4回生
岡本 晃輔さん
(京都市立堀川高等学校 出身)
一日のスケジュール(例)
| 8時30分 | 通学 |
|---|---|
| 9時00分 | 【1限】サスティナブルデザイン論 |
| 10時40分 | 【2限】環境設計Ⅱ |
| 12時10分 | 昼休み |
| 13時10分 | 【3限】設計演習Ⅲ |
| 14時50分 | 【4限】設計演習Ⅲ |
| 16時30分 | 【5限】設計演習Ⅲ |
| 18時00分 | 課外活動 |
資格・キャリア
取得可能な資格一覧
- 一級建築士受験資格
- 木造建築士受験資格
- 施工管理技士資格※1
- 社会福祉主事任用資格
- 二級建築士受験資格
※資格の取得には、大学が定める所定の科目の履修と単位修得が求められます。
※1 受験資格認定対象者は「基礎数学Ⅰ」、「基礎数学Ⅱ」、「建築数学・物理」のなかから
2単位以上履修した者。
主な進路 (2021~2023年度)
| 就職先 | (株)一条工務店、(株)オカムラ、(株)桑原組、大和ハウス工業(株)、タカラスタンダード(株)、(株)竹中工務店、タマホーム(株)、東建コーポレーション(株)、滋賀県、近江八幡市 など |
|---|---|
| 進学先 | 滋賀県立大学大学院、大阪公立大学大学院、京都大学大学院、東京工業大学大学院 など |




